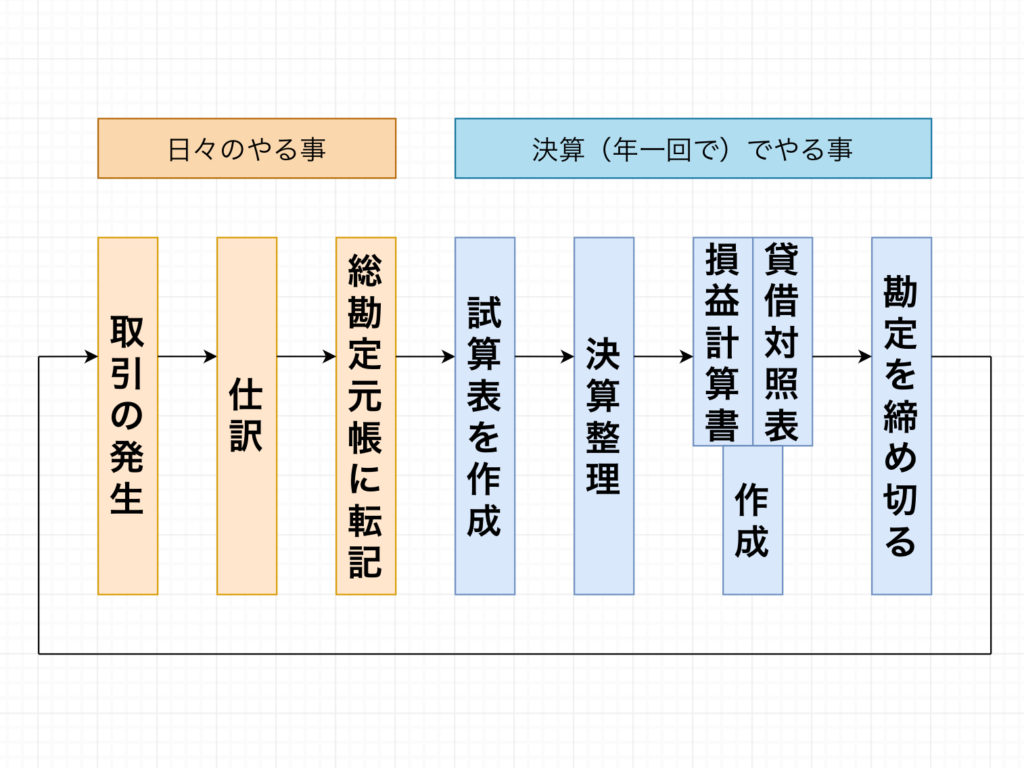
現金
今回の、現金預金の仕分けは『仕訳』のカテゴリーになります。
簿記の中では、「現金」=硬貨、紙幣、以外に金融機関ですぐに、現金化できるものも「現金」に含まれます。
- 他人振り出しの小切手・・・銀行に持って行くとすぐに現金化可能
- 郵便為替証明・・・郵便局に持って行くと現金化可能
- 送金小切手
上記をまとめて通過代用券と言います。
甲社に商品1000円を売り上げ、代金は甲社振り出しの小切手で受けとった
現金 1000 / 売上 1000
他人振り出しの小切手は現金。現金を受け取ったので、借方現金(資産)。
現金過不足
現金過不足とは、帳簿残高(帳簿に記録した現金の残高)と、実際有高(実際の現金の金額)の金額があわない状態のことを言います。
例)帳簿残高1000円、実際有高1200円の時は200円多いことになりますねʅ(◞‿◟)ʃ
この場合の仕訳けは、
現金 200 / 現金過不足 200
と、一時的にこのように仕訳けをします。
イメージとしては、200円分の回収の仕訳けの記入忘れと、この場合は考えておきます。
のちに、200円は売掛金の記入忘れだったことが判明するとします。
現金 200 / 売掛金 200
この仕訳をしていなかったというわけです。
先ほどの仕訳けを合わせてみると。
現金 200 / 現金過不足 200
現金過不足 200 / 売掛金 200
現金過不足を相殺できるので、結果
現金 200 / 売掛金 200
このような仕訳が出来上がります(*´ω`*)
普通預金 定期預金
①普通預金口座に現金1000円を預け入れた。
②定期預金口座に現金1000円を預け入れた。
① 普通預金 1000 / 現金 1000
② 定期預金 1000 / 現金 1000
当座預金
特徴
・ 引き出す時に小切手が必要
・ 利息がつかない
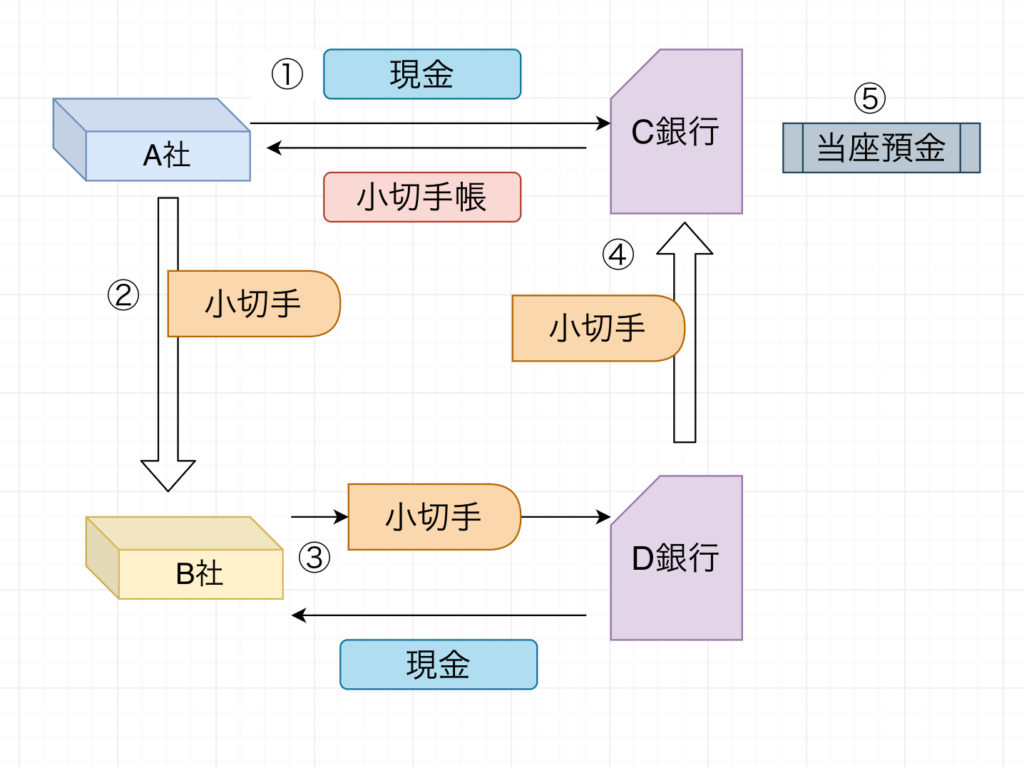
① A社はC銀行に現金を預け、小切手帳を受け取った。
② A社はB社に対する買掛金を支払うために、小切手を振り出した。
③ B社は受け取った小切手をD銀行に持って行き、現金を受け取る。
④ C銀行とD銀行で小切手を交換。
C銀行にあるA社の口座から小切手の金額が引き落とされる。
当座預金の仕訳
甲社は当座預金口座に現金1000円を預け入れた。
当座預金 1000 / 現金 1000
甲社は乙社に買掛金1000円を支払うために小切手を振り出した。
買掛金 1000 / 当座預金 1000
乙社は甲社に対する売掛金1000円を甲社払い出し小切手で受け取り、ただちに当座預金に預け入れた。
当座預金 1000 / 売掛金 1000
例題3の記述に『ただちに〜』と、いう文がなければ以下の仕訳になります。
現金 1000 / 売掛金 1000
その後に、口座に預け入れると...
当座預金 1000 / 現金 1000
と、なります。
小口現金
定額資金前渡法(インプレスト・システム)
流れとして
①会計係が小口係に現金を前渡しします。
②小口係が日々の取引のある従業員などに現金を支払い、小口現金を管理します。
③一定期間後に小口係が会計係に取り引きを報告します。
④後に会計係は小口係に現金を補給します。
簡略化すると
①10000円渡す
②タクシー代3000円使う
③報告
④3000円補給
このような流れです。
月初に会計係から小口係に現金10000円支払われた。
小口現金 10000 / 現金 10000
会計係は小口係から一定期間の支払い報告を受けた。
(タクシー代3000円 ハガキ代1000円)
旅費交通費 3000 / 小口現金 4000
通信費 1000
支払い項目に対する勘定科目
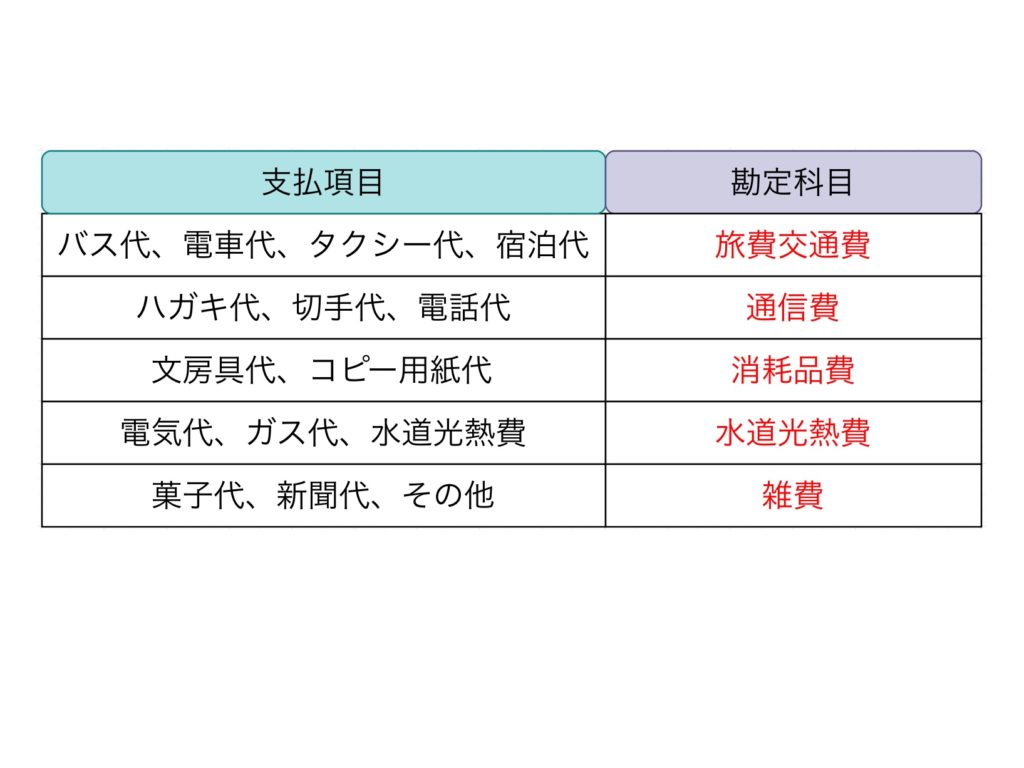
現金預金は以上になります_φ(・_・
ややこしいようで、よく読むと基本にそっているだけなので、落ち着いて問題文を読めば問題ないかと思います。
↑の支払い科目は慣れるまで、戸惑うかもしれませんが...丸暗記しちゃいましょう(*゚▽゚*)
次回は、手形・電子決済債権(債務)です!
では、また_φ(・_・







